-
- ■産学連携
- 国際交流
- ダイバーシティ
- 情報理工学の創造的展開プロジェクト
- 受賞・表彰
profile
東京大学 大学院情報理工学系研究科
知能機械情報学専攻 准教授
略歴
2003年 東京大学大学院工学系研究科(産業機械工学専攻) 博士課程修了、博士 (工学)。東京大学大学院情報理工学系研究科(知能機械情報学)准教授(現職)。
神経工学、感覚代行デバイスの開発、聴覚生理学など、医学・工学の境界領域の研究に従事。
ホームページ:
http://www.ne.t.u-tokyo.ac.jp/index.html
医工連携が声高に求められるようになって久しい。情報工学と医療分野の連携はAI診断をはじめとする最先端システムとして形を表し始めている。高橋宏知准教授はエンジニアの手法である「リバースエンジニアリング」を使うことで脳の理解を進め、難病の治療法やAI診断など医工連携研究を強力に推進してきた。そのユニークな発想は「役に立たないことをやる」という高橋准教授ならではの価値観が源泉となっている。研究者の役割、教育者としての考え方、情報社会の未来といった話題を、斬新な切り口で語っていただいた。
(監修:江崎浩、取材・構成:近代科学社編集チーム)
Q.先生の研究について簡単に教えていただけますか
高橋——脳をリバースエンジニアリングするという研究を進めています。リバースエンジニアリングとは物を作ることの逆、つまり製品を入手して分解や解析などを行い、動作原理や設計や思想を理解することです。この方法で機械を理解できるのであれば、同じ方法を使って脳を理解することもできるんじゃないか、という着想です。エンジニアとしてなんとか自分のやり方で脳を理解したいというのが一番大きなモチベーションですね。
Q.先生は工学部に所属しながら脳をはじめ医療系の研究テーマを選ばれていますが、興味を持たれ始めたのはいつ頃でしょうか
高橋——私は学部生の頃、東京大学の畑村洋太郎先生の研究室に所属していまして(図1)、設計のイロハをたたき込まれました。加えて当時の東京大学の機械科は従来型の重厚長大なシステムだけではなくナノテクノロジー、情報学、医療、生物、脳科学など異分野のフロンティアを開拓しようという機運が高まっていた時代だったと思われます。そこで畑村先生に「高橋君、これからは医療工学の時代だよ」と言われ、東京大学医学部耳鼻咽喉科の加我君孝教授のもとで研究を始めました。
Q.医学部ではどのような研究を?
高橋——一番最初の研究は、喉頭を摘出した患者さん、喉頭がんで声を失った患者さんの発声システムを作るという試みです。入れ歯の中にスピーカーを組み込んで、口を動かすと喋れない人でも声が出せるようになるというものを開発しました。いろいろなフィードバックを頂いたおかげもあって、評判は良かった。だけどその研究は続きませんでした。
Q.それはどうしてでしょう?
高橋——その後ちゃんと論文にしようと思って調べてみると、1950年代ぐらいに同じ物を作っていた人がいたんですね。畑村先生に報告したら大笑いされました。まさにこれは失敗学の話なんですけど。
Q.畑村先生の『失敗学のすすめ』ですね。
高橋——ええ。事前に調べる、ちゃんとサーベイしないとこういうことになるんだぞ、というお手本のような話です。とにかく、発想自体は良かったのでしょうけど、当時は学部生でしたし、患者さんの望むものが作れるようなスキルも持ち合わせていませんでした。要は、本当にプロフェッショナルな企業が作ればもっと完成度の高い素晴らしいものができるのだろうと思ったんです。
Q.ベンチャーという選択肢は?
高橋——確かにその頃、ベンチャーを作ってみてはという話はありました。そこで冷静に計画を立ててみたんです。喉頭摘出した方が日本に2万人いて、月に大体50人ぐらいの方が手術されている状況と仮定して、彼らが使っている発声システムを大体10万円ぐらいと見積もり、シェアを何%取っていくらで売って……計算すると自分一人が食べていくのがやっとだった。
Q.そこで大学に残るという選択をされたのですね?
高橋——企業側が持っている資産やノウハウを使えば、たとえニッチ産業だとしても成り立つし、もっと完成度の高い製品を患者さんに提供できるでしょう? 今まさに困っていることをなんとかするのは企業の領域なんです。大学が同じことをやる環境かというと、私は違うと思って。そこで大学に残ってドクターになったとき、自分はなにをすべきなのかと考えました。私は、もっと役に立たないことをやろうと決めました。
Q.役に立たないこと、でしょうか?
高橋——ええ。誤解のないように言えば、今は役に立たないけどもっと将来には役に立つようなことです。私は次の研究で、脳を電気刺激して耳が聞こえない患者さんの聴覚を再建することに挑戦しました。刺激部位は脳幹です。ただ脳幹を電気刺激して聴覚再建できるかは定かではない。まずは基礎研究としてラット(ドブネズミ)の脳幹に刺激電極を埋めて、大脳皮質の聴覚野に貼った電極から聴性脳波を抽出しました。そうしてネズミが音刺激に反応しているかを確かめているうちに面白いと感じて、本格的な脳の研究を始めました。脳の理解は将来必ず役に立ちます。
Q.なるほど。それで脳の研究を続けられてきたのですね?
高橋——そうですね。たとえば今は脳の理解のためにネズミの学習の研究をしています(図2)。簡単な実験で、音が鳴ったときにスイッチを押したら餌が出る仕掛けを作って延々とやる。そうするとネズミは大体できるようになるわけですが、やっぱりネズミにもできる子とできない子がいて、できる子はあっという間にできるようになって、そのまま最後まで優等生なんです。
Q.個体差が結構あるのでしょうか?
高橋——はい。できない子は最後までできない。更にできる子とできない子の間にもいろいろなタイプがいて、最初は調子がいいけどそのうち頭打ちになる子とか、最後ぐんと伸びる子とか違いがはっきりしています。そういった行動を観察します。特徴的なのは、まず最初は様々な探索行動をしなくてはいけないのですが、学習の序盤でいい成績を収める子は試行錯誤する、探索するタイプが多い。
Q.好奇心が強いということでしょうか?
高橋——そうなのでしょうね。で、後半いい成績を収める子は無駄なことをしない。スイッチの前にじっと立って、ピッと鳴ったらピッと押す。学習して最適化しています。そういった個体の脳の活動を調べてみると、学習序盤でいい成績を収める子たちの脳の活動はものすごく大きい。神経細胞の活動の多様性も豊かです。そして学習の終盤の反応を調べると、できる子ほど音に対する活動が小さい。無駄がないのでしょう。ここから多様性と最適化という二つの軸が見えてきます。
Q.多様性と最適化についてもう少し詳しく教えてください。
高橋——これも学生さんの研究ですが、シャーレの上にネズミの神経細胞を育てる実験を行いました。すると勝手に活動を始めるんです。その神経細胞をロボットにつなぐとロボットは勝手に動き始める。自律ロボットですよこれは。面白い動きではあるけれど、でも混沌とした活動をロボットの動きとして可視化しているだけなんです。次に、この神経回路にフィードバックの刺激を与えてうまく最適化してあげると、まっすぐ歩けるようなる。そして簡単な迷路ならば脱出できるようになる(図3)。これは賢く見えますよね? 人工知能や脳を語る上ではまさに賢さ、知能とはなにかを定義する必要があるだろうと思っています。脳の場合、これは多様性と最適化という二つの軸で説明できるでしょう。
Q.賢さの評価ということでしょうか?
高橋——賢さには実体がないんですよね。じゃあ脳や生物に対してどういうときに賢いと思うかというと、なにかの仕組みを作って混沌から秩序が出てきた瞬間に賢さを感じる。それが「知能とはどういうものか」という説明につながるはずです。なにかを識別しましょうとか、なにかを回帰分析しましょうとかいうタスクはそれに特化したマシンを作れば事足りますが、私が魅力を感じる「知能」はそこにはないですね。もちろん人間よりも早く正確に識別や回帰分析できるマシンにも、ある種の「知能」や「賢さ」は感じるのですが、私が脳や生物に感じる知能とは何かが違います。
Q.工学者として脳を理解するためにどのような方法を?
高橋——たとえば医学部のお医者さんは顕微鏡で新しい細胞を見つけてその機能を調べようとするし、臨床のお医者さんは脳の形態と症状の関係性を研究するでしょう。いわゆる帰納的な理解です。一方で我々のような工学部、情報系の人間が「脳ってこうなってるんだ」と理解する方法としては、システムの方面から探る。たとえば脳というのは究極の省エネマシンだったりする。これはどういう仕組みなのか、という追求です。
Q.省エネマシンのお話をもう少し詳しく聞かせてください。
高橋——脳はたった20ワットで動いています。それでいろいろなことができてしまう。その代わり脳は割といい加減にできています。人間は失敗しますよね。だから自動運転のような複雑な動作を、失敗しないよう実現することを目指したときは、脳に学ぶよりディープラーニングでガチガチにシステムを構築してしまったほうが逆に事故率が下がるかもしれません。
Q.工学的なシステムとは違って、脳は基本的に自由ということでしょうか?
高橋——はい。だから自発活動――なにも入力していないのに勝手に動くわけです。なぜ動くかといえば、脳は熱揺らぎによってイオンチャネルのタンパク質の形が変わって電気信号が出てしまうから。脳はいわゆるノイズで動いている。逆にパソコンがなぜこんなに電力を消費するかといえば正確に動作しているからです。ノイズを許さない。
Q.ノイズを前提としたシステムなのでしょうか?
高橋——脳はノイズにとても強い、というかノイズを利用する計算アルゴリズムを持っているのでしょう。GANのような仕組み、つまりノイズからそれらしいイメージを作り出してしまう仕組みが脳のどこかに入っているのかもしれない。だからこうしたシステムを組み合わせることで意識のようなシステムもできるのではないかと考えています。
Q.逆に脳を模してなにかを作ろう、というのは相当難しいのでしょうか?
高橋——そのためにはリバースエンジニアリングで「脳って一体どういうことを実現するためにあるのか」をしっかり記述できるかにかかっているでしょう。
Q.これからの情報社会がどうなるか、先生の中でビジョンはありますか?
高橋——意識システムの解明が重要だと思います。意識があるシステムと意識がないシステムができるその違いは一体なんなのか。意識があるシステムだからできることはなんなのか。その解明には生成ネットワークの研究も必須です。ディープラーニングのように情報識別するだけでなく、識別した情報を基にして新しい情報生成するようなネットワークが脳にもあるはずなんです。それがなにかしら有機的につながると、意識そのものではなくても、意識の種みたいなものができるかもしれない。
Q.意識の役割を明確にするということでしょうか?
高橋——そうですね。脳は外部から入力される莫大な情報を並列計算していると考えられていますが、意識に残る情報はその一部で、その情報には明確な時間軸がついています、つまり並列ではなくシリアル(逐次的な)計算になります。
Q.時間軸が付くとどうなるのでしょう?
高橋——なにが先に起こったか分かるので因果推論が可能になります。その部分がうまくいかないと、たとえば統合失調症のような機能不全が起こるかもしれない。人間が因果性を見出すのは実は脳が勝手にやっていることではないか、と私は推測しています。だからその機能が強過ぎると病的になるし、弱過ぎると鈍い人となってしまいます。因果推論がないと科学も宗教も生まれなかったかもしれない。つまり将来的には、意識を持ったロボットによって宗教が作られるかもしれません。
Q.面白いですね。自発・自律的な脳の機能とも密接につながっていそうです。
高橋——ええ。それらは自律的なエージェントという形で身近に現れるでしょう。ただこの自発・自律的な活動は先に説明したように割といい加減です。許容できる領域はエンターテイメント業界しかない。人間のように個体差がしっかり出てくるエージェントを眺めているのは面白いと感じるはずです。コンピュータは間違いのないよう正確に動作しますが、同じ動きしかしないので面白みがありません。もう少し「自律性」の社会的要望があればいいのですが。
Q.育成ゲームのような楽しみ方ですね?
高橋——そうですね。一方で、そうしたある種のいい加減な動きというのはインタラクションすることで制御できるのではないかと考えています。たとえば音楽を聞くと集中力が上がるのはなぜかといえば、音楽が脳のダイナミクスを変えているからです。音楽と脳がインタラクションし合っている。行く末は攻殻機動隊の世界のように脳にチップを入れて、電気エネルギーでもっとダイレクトに動かすような仕組みができてもおかしくない。それは医療にも応用できて、認知症やてんかんの抑制も可能とするでしょう。リバースエンジニアリングによって脳がエンジニア流に理解できれば、そんなアプリケーション開発も夢ではありません。
Q.研究とビジネスの関わりをどうお考えでしょう?
高橋——起業家でもあり投資家でもあるピーター・ティールという方は、多くの人にとって真ではないこと、多くの人が違うと捉えているが自分は真だと思っていることがとても大切だと仰っています。その観点から私は、徹底的に競争して勝つか、競争を避けるかという二つの戦略があると考えています。
Q.具体的にはどのような?
高橋——たとえば人工知能はほとんどの方が金脈だと考えているかもしれませんが、そこから一線を引くことも大事かもしれない。個人的には、周りの人が真だと思っていないことで、自分が正しいと思えることを楽しく研究していきたいですね。
Q. レッドオーシャンで戦うのは避けるべきと?
高橋——周りが重要だと思っていることでお金を稼ごうとするなら、相当戦わなくてはいけないですよね。一つの手段として、産学連携を進めて大学発ベンチャーを作るというのは大いに結構なことだと思います。スキルがあればお金がない人でもスタートアップできるような環境が整っているし、いわゆる東京大学の情報理工学のシンボルとして活躍してもいい。ただ繰り返しになりますが、私自身がどうしたいかと問われれば、競争とは一歩距離を置いた場所で楽しく研究をしたい。大学はどちらも許容できるサスティナブルな面を持っていると思います。
Q.先生は楽しく研究をする、という基準を崩さないようにしていると?
高橋——私にとって楽しく研究をするとは、何をすべきか自分で考えるということですから。あとビジネスの話に限りませんが、大学の研究者の役割もあるでしょう。私は耳鼻科医や脳外科医、精神科医と共同研究することが多いのですが、臨床系はAI診断がものすごく活気があります。ですが、お医者さんからこうしたいという具体的な提案はあまりない。彼らもなにをどのように実現すべきなのか明確なビジョンを持っていないことが多いんです。
Q.現場のお医者さんでも問題を把握していない?
高橋——従来とは異なる方法で解けそうな問題を設定するのが難しい、ということだと思います。なのでこちらから提案することで物事が進むことが多い。たとえばお医者さんに脳波の時系列データ解析をお願いされたとします。脳波の時系列解析は他の研究者がたくさん参入しているので、同じようなことをするのではなく、脳波データを脳波計に写すような写真にしてディープラーニングに食わせましょうと提案してみたところ、トントン拍子でうまくいった。そうした提案力といいますか、アイデアをぽんと与えてあげられるのが我々、工学系研究者の役割かもしれません。
Q.では、これからのビジネスについてどうお考えですか?
高橋——日本の年金制度は経済成長率年3%成長することを前提にしています。ただこれはかつて日本が7~8%成長していた時代に作った制度で、競争していれば商機があるという時代でしか成り立ちません。競争して成長しないと保たないシステム自体がこれから破綻するかもしれない。そのとき企業は、個人はどうするでしょうね。今は勝たないと安定できないでしょうけど、勝つだけが全てではなくなったら、競争以外の道を探る人が増えるかもしれません。目先の利益だけではなく、役に立たないことを追求する生き方もあるでしょう。科学者でいえば、本来は利益は深く考えず、とにかく真理を追究しみんなの知的好奇心を満たすのが役割です。そのような活動を支援する場所を提供するのが大学の役割の一つであると、社会的にもっと認識されるといいと思います。
Q.学部時代のお話で触れられた観点ですね?
高橋——ええ。たとえば当時の私はネズミの聴覚のことしか知りませんでした。論文は書けるけどなんの役に立つのか分からない。それが好奇心の赴くまま楽しく研究していくうちに段々と聴覚自体のことが分かるようになり、聴覚が分かると視覚のことも分かるようになり、ネズミが分かればヒトの脳もなんとなく分かるようになってきた。そして脳の視点から人工知能を考えるようになった。そうするといろいろな人の技術的な疑問や社会的な問いにも、自分なりに答えられるようになってきた。ジェネラリストには簡単なことではなれません。
Q.ジェネラリストというお言葉が出ましたが、先生はジェネラリストを目指そうとお考えだったのでしょうか?
高橋——昔、立花隆さんにすごく憧れていたんですよ。彼の書く本はどれもこれもマニアックだけど面白くて。だけど指導教員の中尾政之先生に「ジェネラルっていうのは後から付いてくるものなんだ」と指摘されまして。今となってはそのとおりだと思います。ヲタクのような研究でも、腐らないで続けることが肝要ということですね。
Q.学生さんをエキスパートに育てるためのポリシーをお聞かせください。
高橋——自分が面白いと思うことをする。あと、意思決定を自分でする。「なにに興味があるのか」から始めて「じゃあこういうのどう?」と進めて「それいいかもしれない」と段階を踏んで決めていくわけです。先生に言われてやるのではなく、自分が面白いと思って始める研究でないと、本当にいい成果は出ないと思っています。そこを突き詰めないで文句ばかり言っていた学生さんは、希望の企業に行ったはずなのにそこでも文句を言っている。ネズミの研究を熱心にやっていた学生さんは就職後も楽しそうにやっていたりする。どの分野でも一生懸命にやることが大切だと思います。
Q.先生の研究室に入るメリットはなんでしょう?
高橋——研究室の学生さん(図4)の弁ですが、情報系に入ってくる学生さんはプログラミングをやりたい、人工知能を学びたいという具体的な目標や意思を持っている方がほとんどでしょう。でもそれは結局、企業に入った後でもプログラミングの研修はあるし人工知能の勉強会もある。だから将来役に立ちそうなことを一辺倒に学ぶのではなく、普通の会社では体験できないこと、たとえば細胞を培養したり生の脳を見たりすることを通して、社会で役立つ情報工学のスキルも身に付けられることが大きなメリットかなと思います。誤解のないように付け加えておくと、生モノの実験ばかりではなく実際には自分で実験系を作るとか、大量の実験データを機械学習で解析するとか、現場で実践的な問題に取り組みエンジニアとしてのスキルを磨くことができます。
Q.情報系の企業の中では触れられない分野の知見、ということでしょうか?
高橋——そうですね。工学は実学ですから、次世代の人工知能を語るためにも脳の実物を見て、自分の手でいじってほしい。その経験は就職でも有利になると思います。自分が人事部長になったつもりで「僕はプログラミングがとても得意で即戦力です」という人と「プログラミングに加えてネズミの実験をたくさんやって研究結果を出してきました」と楽しそうに話をする人を比べた場合、私なら後者に興味を持つ。私も修士課程の頃に就職活動をしましたが、ネズミの研究の話をすると面接官はとても興味をもって食いついてきましたよ。そういう貴重さが身につくわけです。
Q.畑村洋太郎先生の失敗学のご指導を受けたということですが、そこで得られた教訓などを学生さんにフィードバックされることもメリットなのかなと思います。
高橋——私もまだ2カ月に1回ぐらい畑村先生の事務所に勉強しに行っていますよ。いま産業界でなにが起こっているのかといった、畑村先生が現場に行かれて感じられたことをそのまま話してくださる。本当にありがたいですね。
Q.たとえば学生さんが失敗したとき、畑村先生の言葉が引用されたりとか、そんなこともあったり?
高橋——まあ日々失敗なんですよね。失敗したときはもう励ますしかない。「もう一回頑張ろう」って。
Q.研究室に向いているのはどういう学生だと思いますか?
高橋——好奇心旺盛な人ですね。端から見て狂っているんじゃないかと思うようなことをやってみたがる人。先ほども言いましたが、やっぱり一番大事なのは、他の人は重要だと考えていないけれど自分はとても重要だと捉えている、という視点を持つことです。人工知能の研究にしても、従来のアプローチではなにか物足りないなと思う子の知的好奇心を満たしてあげられるような場を提供したい。
Q.学生さんには将来的にどうなってもらいたいとお考えですか?
高橋——やっぱり普通の人が考えないようなことをやってほしいと思いますね。ただ逆説的に、それを貫くには一生懸命勉強しなくてはいけません。「これまで」をしっかりと把握した上で「まだ誰もやっていないこと」を「だからやりたい」と言えるようになってほしいのです。今の学生さんは凄く真面目で勤勉な方が多い印象ですが、みんながやっていることをやりたがる。その次は他の人がやらないこと、他の人が大切だと思っていないけど自分が「これはいける」と思ったことに挑戦してほしいです。
Q.先生が情報以外の分野で注目されている研究、あるいは注目されている研究者の方はいらっしゃいますか?
高橋——東京大学 先端科学技術研究センターの30周年企画で、池内恵先生と対談したのは面白かったですね(https://30th.rcast.u-tokyo.ac.jp/future/future01.html)。池内恵先生はイスラムの専門の先生で、宗教がどうして起こるのかという話を熱く議論しました。あとはいつもお世話になってる池上高志先生。
Q.池上先生は人工生命の研究を行われていますね?
高橋——彼とは機械人間「オルタ」というアンドロイドをネズミで動かしましょうと計画して、一緒に申請書も何回か書きました。連戦連敗ですけどね。
Q.逆に文系の分野ではいかがでしょう?
高橋——ぜひ聞いてみたいなと思うのは芸術、アーティストの方ですね。アーティストがどういうことを考えて絵を描いているのか、音楽を作っているのか、演奏しているのか。そういった情報はとても貴重です。研究者も、研究を通じて感動を生み出さなければならないので、ある意味ではアーティストであると私は思っています。なので我々と共通する視点、逆に異なる視点を炙り出せると面白いでしょうね。
Q.アーティストの脳波を測るというお話ではなく?
高橋——彼らの視点がどこにあるのかを知りたいということですね。実は僕の奥さんも音楽家なんですけど(笑)。陶芸家なんていいかもしれないです。
(取材日:2020年3月25日)
1 畑村洋太郎:東京大学 名誉教授。「失敗学」を提唱し、失敗学会の理事長として失敗学の普及を行っている。東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会委員長など、官民多数の調査委員会や有識者会議の委員も務める。
2 GAN:Generative Adversarial Networkの略称。2014年にイアン・グッドフェローらが発表した深層学習のアーキテクチャ。 二つのニューラルネットワークを互いに競わせて入力データの学習を深めていくことから、敵対的生成ネットワークとも呼ばれている。
3 攻殻機動隊:士郎正宗原作のマンガ、およびそれを原作とするアニメシリーズのタイトル。サイバーネット技術や電脳化が一般的に普及したサイバーパンク的世界観の近未来日本を舞台に、主人公草薙素子が率いる公安警察機関『公安9課』の活躍を描いたSFポリティカルアクション作品。
4 ピーター・ティール(Peter Andreas Thiel):アメリカ合衆国の起業家、投資家。PayPalの創業者のひとりであり、シリコンヴァレーで現在も絶大な影響力を持つ。
5 レッドオーシャン:競争の激しい既存市場のことを「赤い海、血で血を洗う競争の激しい領域」として例えた比喩表現。対義語として、競争のない未開拓市場である「ブルーオーシャン(青い海、競合相手のいない領域)」がある。
6 立花隆:日本のジャーナリスト・ノンフィクション作家・評論家。政治、経済、生命、宇宙論まで幅広い評論・執筆活動を続け、「知の巨人」のニックネームを持つ。「失敗学」の命名者でもある。
7 機械人間「オルタ」:東京大学 池上高志教授、大阪大学 石黒浩教授らによって作られたアンドロイド。CPG(Central Pattern Generator)とニューラルネットワークによるシステムで、生命らしさや人間らしさがどこまで表現できるかに挑戦した機械人間。詳細はこちらhttps://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00026.html
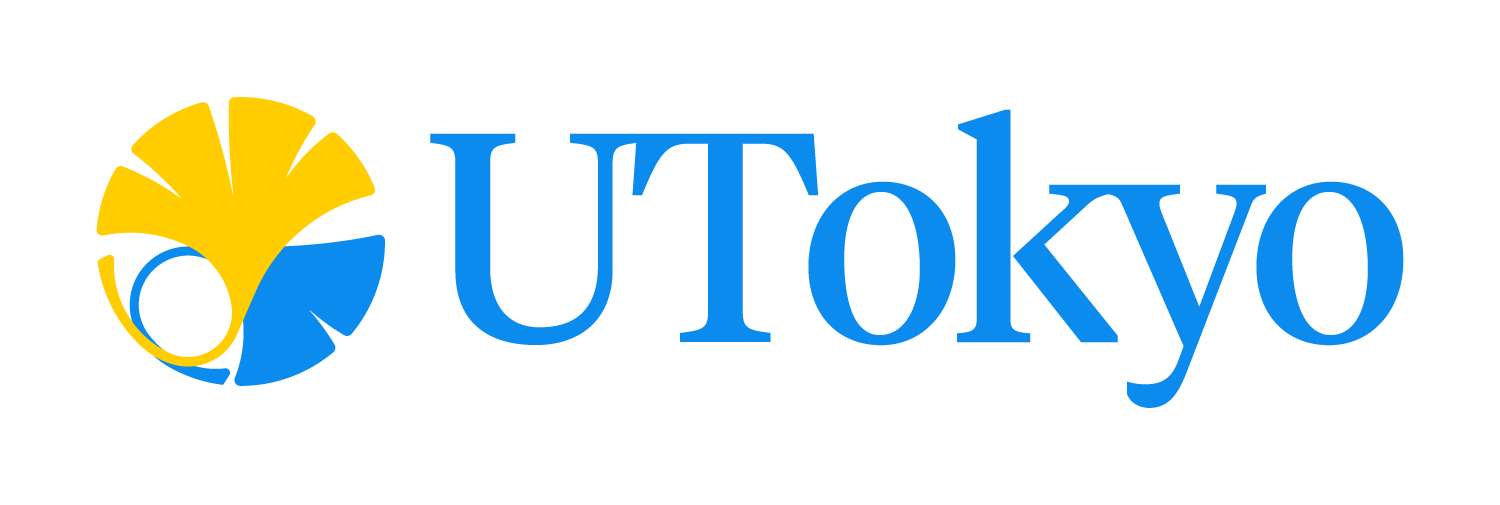
Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo