-
- ■産学連携
- 国際交流
- ダイバーシティ
- 情報理工学の創造的展開プロジェクト
- 受賞・表彰
 |
ここに10年前(1996年)に発行された1冊の本『アールキューブ(R3)』がある。21世紀のロボティクスの研究動向を大胆に予測した本だ。通産省アールキューブ研究会編によるものだが、構想を練り上げたのは、産学官の機械、電子、メカトロ、制御などの研究者。その推進役(構想委員会委員長)が当時、工学系研究科計数工学専攻の舘教授である。
現在はネットワークの時代。ネットワークを介して、世界中でいろいろな情報を自由にやり取りしているが、1995年にそれを先取りし、実時間遠隔制御によって人の行動がロボットに伝わっていく仕組みを構築する「リアルタイム・リモート・ロボティクス(Real-Time Remote Robotics : 実時間遠隔制御ロボット技術)」構想がまとめられた。アールの立方体という意味から『R3』と表現し、その壮大なイメージを初めて出版物として明らかにした。この未来予想は色あせるどころか、今も輝きを増し、10年前に描かれたロボット研究のシナリオは、脈々と受け継がれている。「10年経って、どこまで達成されたかと問われれば、まだまだ道半ば」と舘教授。当時のビジョンが壮大かつ斬新だった証拠である。
 |
舘研究室では、バーチャルリアリティー、ロボティクス、コミュニケーションの3つを柱に掲げている。研究領域は触原色や光学迷彩も含めて幅広いが、その中で、「特徴的なオリジナル研究を1つだけ挙げて」と無理強いすると、舘教授はおそらく『テレイグジスタンスによるロボット研究』と答えるに違いない。それは『R3』によって大きく展開したものであり、自ら提唱した概念、そして、3つの研究領域の融合分野だから。
1980年、日米で同時期に新しい研究のアドバルーンが上がった。人はコックピットの中にいて、そこから指令を出すと、少ないながらも知能を持ったロボットがその指令に従って作業をする。これだけだったら、ロボットの遠隔操作にすぎないが、人がロボットの中に入り込んで、人がその場にいるような感覚でロボットを制御する。こうなると俄然、位置づけが異なってくる。これがテレイグジスタンスの概念(遠隔“存在”技術)で、日本で独自に提唱したのが舘教授だ。この概念が、人がロボットと一体になって、自分の分身のように自在に行動する分身ロボット研究の出発点となり、その具体例が「テレイグジスタンスロボット」である。
それを実現するには、人が首を動かし、目を動かして実際に見ている視覚情報と同じ情報をロボットも見られるようにすることだ。そこで、人間の運動を計測してロボットに搭載したセンサーを動かし、ロボットと人が離れていても同じ情報をとらえられるシステムの開発に成功した。「このシステムで、自分を見ている自分自身の姿を見るという不思議な体験をしたときの感動は、今でも鮮明に残っています」。
ロボットをオフィスに置いておくと、本人が海外出張していても、ロボットに入り込んできて、オフィスでだれかと直に面談することだってできるだろうし、危険な災害現場や離島などに置いた多数のロボットを遠隔存在技術によって活用する道も拓かれよう。高齢化社会でクローズアップされる介護にしても、ロボットが介護するのではなく、遠隔地から家族や親しい知人がロボットを分身として利用することで、人の顔が見える温かみのある新しい介護が実現する。そうした時代に向けて技術は着実に進歩し、視覚、聴覚、触覚情報を伝えたり、ロボットがモノを持ち上げられるようになった。
 |
| テレサフォンでは、操縦者の顔が遠くに置いたロボットの顔の部分に映し出されている |
それをさらに深化させるために、近く舘研究室(本郷キャンパス)と東京・お台場の日本科学未来館をネットワークで結んで、相互テレイグジスタンス実験を行う予定だ。これには当面、TWISTERと呼ぶ全周囲裸眼立体ディスプレーを用いるが、次のステップとして、2006年度のグッドデザイン賞を受賞した、遠隔コミュニケーションを支援するロボットシステム「テレサフォン」を使用する計画である。テレサフォンは、経験をユビキタスに共有できるロボットの新しいアプリケーションを開拓し、従来のバーチャルリアリティーを打ち破って、操縦する人を現地に飛ばす新しい楽しみ方を提案するものだが、この実験を通して、単なる“臨場感”から究極の目的である“存在感”へとジャンプさせる。
人が遠隔空間を通ってロボットに入り込むだけでは、ロボットと相対しているという感覚を拭いきれない。それを払拭するために、実物があたかもそこにあるように見せられる再帰性投影技術を駆使し、ロボットではなく、その使用者がすぐそばにいるかのようにコミュニケーションできるシステムを目指す。飛躍への一歩がまもなく刻まれる。
舘教授が所属する情報理工学系研究科は、情報科学技術の組織基盤を整備し、新領域を拓くことを目標に2001年に設けられた。最も若いこの研究科が中心となって、21世紀COEプログラム研究を推進した。実世界を標榜するこの21世紀COE研究は、多くの成果を挙げて2006年度で終了し、再展開される予定だが、さらにその先を担う理念が求められる。舘教授は「数理、物理などと同じ土俵で、『情理』の構築が必要ではないか」と提案する。コンピュータ科学、創造情報学など6つの専攻を『情理』という新しい学問で横串を刺し、研究のアクティビティーを一段と高めて革新的な研究を展開する―情報理工学系研究科の発展を期す舘教授のメッセージである。
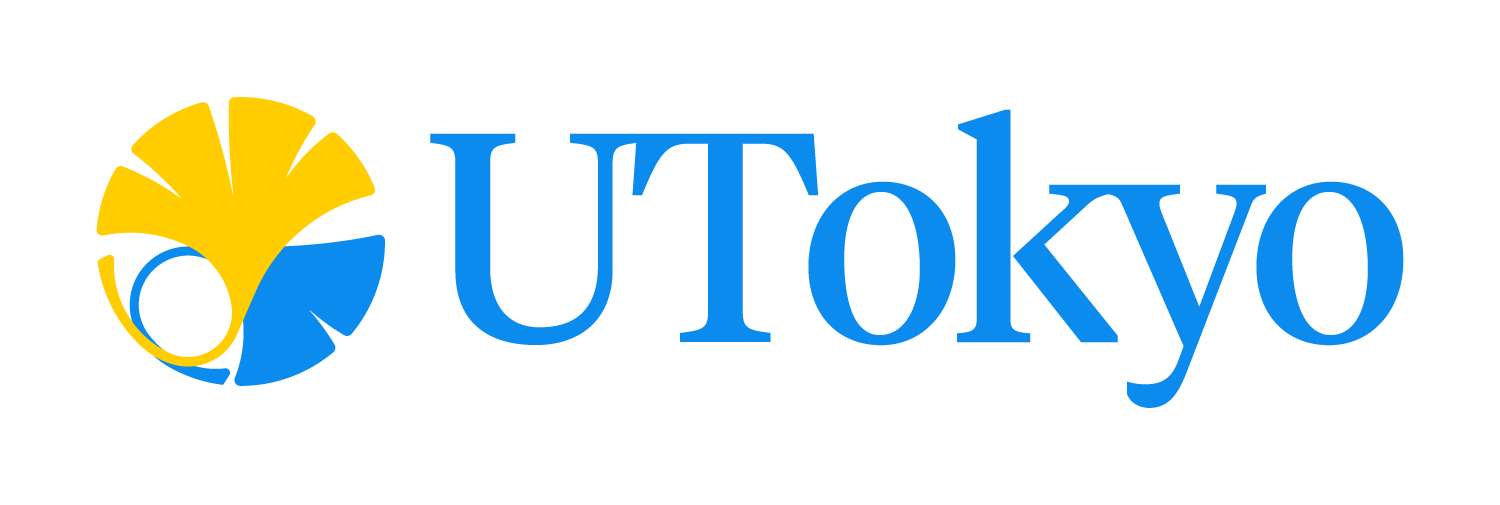
Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo