会期:9月4日(木)~ 9日(火)
開館:10:00~19:00
会場:Kunstuniversitat
(University of Art and Industrial Design Linz, Hauptplatz 8, 4010 Linz, Austria)
東京大学アルスエレクトロニカ2008 キャンパス展実行委員会(委員長:廣瀬通孝・知能機械情報学専攻教授)は、9 月4 日(木)から9 日(火)まで、オーストリア・リンツ市で開催される世界最大級のメディアテクノロジーとメディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ2008」の招聘をうけ、キャンパス展「Ars Electronica Campus 2008: Hybrid Ego - The University of Tokyo」を開催する。東大におけるメディア芸術に関する研究群(CREST:デジタルパブリックアートを創出する技術等)をはじめとしたプロジェクトや、大学院情報学環を母体とする学際情報学府・コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム制作展、メディアミュージアム展示学講義、メディアリテラシーワークショップなど、多様なプロジェクトの成果を世界に向け発信する。リンツ市の建物(University of Art and Industrial Design Linz)1棟すべてを借り切って行う東大としては珍しい試みで、情報理工、情報学環、生産技術研究所、先端科学技術研究センターの研究室グループが24作品を展示する。
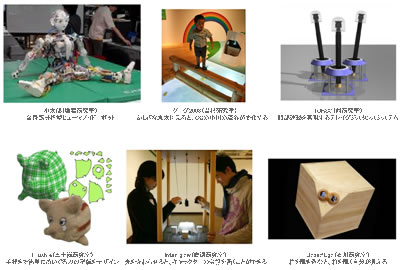 |
| 展示する作品例 |
|
※画面をクリックして拡大画像をご覧下さい |
アルスエレクトロニカ・フェスティバルは、1979年からオーストリアのリンツで開催されている芸術・先端技術・文化の祭典で、世界最大級のメディアアート(主に、コンピューターなど複製芸術時代以降のメディアを用いた芸術作品)に関するイベント。2009年に30周年を控えており、例年10万人以上が世界中から訪れている。毎年、アートとメディアテクノロジー、現代社会に関する今日的なテーマを掲げ、最先端のテクノロジーを用いた作品の展示、電子音楽のライブやパフォーマンス、気鋭のアーティストや批評家、キュレータ、ジャーナリストによるカンファレンス、キャンパス展(学校展示)など、数多くのイベントが開催される。
例年、日本からも多くの作品が受賞・出展され、メディアテクノロジー分野における日本の優位性を、ヨーロッパだけでなく全世界に向けて広く発信するイベントとなっている。今年は「新しい文化経済=知的所有権の限界」(A NEW CULTURAL ECONOMY = The Limits of Intellectual Property)をテーマに、多彩な催しが行われる。
一方、アルスエレクトロニカキャンパス展は、2001年から始まった同フェスティバルのイベントの1つ。アートとテクノロジーの統合を図るメディアアート教育を行っている学校を紹介するもの。従来は美術学校など芸術を専門とした教育機関が主に参加してきたが、本年度は総合大学から東大が初めて選ばれ、キャンパス展を行うことになった。
近年、領域横断的な表現=「ハイブリッド・アート」(ロボット技術やIT 技術を芸術と融合させる取り組みなど)が注目を集めている。東大で実施している、メディア芸術に関するCRESTの研究群をはじめとするプロジェクトの成果が情報技術分野で世界に認められていること、IRTプロジェクトなどロボット技術と情報技術に関するユニークで先導的な取り組みなどが評価され、選ばれた。
 http://www.aec.at/en/festival2008/program/content_event.asp?iParentID=14383 http://www.aec.at/en/festival2008/program/content_event.asp?iParentID=14383
| 実行委員長 |
: |
廣瀬通孝(情報理工学系研究科教授) |
| 実行委員 |
: |
荒川忠一(工学系)、池内克史(生産技術研究所)、稲葉雅幸(情報理工)、舘暲(情報理工)【以上教授】、五十嵐健夫(情報理工)、苗村健(情報理工)、水越伸(情報学環)、森山朋絵(情報学環)【以上准教授】、川上直樹(情報理工)、筧康明(慶応大学)、吉海智晃(情報理工)【以上講師】、アルバロ・カシネリ(情報理工)、工藤俊亮(生産技術研究所)、鈴木太朗(情報学環)、鈴木康広(先端科学技術研究センター)、新居英明(情報理工)、西村邦裕(情報理工)【以上助教】、渡邉淳司(さきがけ研究員)、岡部理加(事務)(役職別、敬称略) |
|